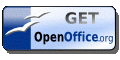♯♭は楽譜によく登場する記号(臨時記号)です。
中学の音楽の時間に、この記号が五線譜に書かれていて「さてこの曲は何調の音階でしょう?」とか、
「ト長調の音階を五線譜に示しなさい」などと言う問題がありました・・・
この場合の♯♭は臨時記号とは言わないで調号と言うようです。(臨時じゃないですからね)
何それ?と言う感じでしたが
5度サークルを知っていれば簡単に解答できましたね。
5度サークル(Circle of fifth)とはサークルを時計のように12分割し、ド(C)からスタートして5度ずつ進行。
ド・ミ・ソのソ(G)、ソ・シ・レのレ(D)みたいな感じですね。
※3和音は1度・3度・5度なので5度の音は3和音から導き出すと指折り数えなくて済むので速いですね。
そして出来たのが5度サークル。

♯や♭が付く数はこの時計の時間に比例。
たとえばミ(E)の場合は4時なので♯が4個です。
反時計方向の場合は♭の数がわかります。(12-時間)
たとえばシ♭(B♭)の場合は10時なので12-10時で♭が2個ですね。
5線譜のどの位置に書くかもわかります。
#ならファ(F)からスタートして時計回りに1個づつ追加。
たとえば上の例でミ(E)の場合は♯がファ(F)・ド(C)・ソ(G)・レ(D)です。
♭ならシ(B)からスタートして反時計回りに1個づつ追加。
たとえば上の例でシ♭(B♭)の場合は♭がシ(B)・ミ(E)です。
と、言うことで、丸暗記するよりも覚えやすと思います。
それよりなによりこの5度サークルはあのピタゴラスさんが発明したそうです。
素数がどうのこうのと数学的に成立する理由を考えると逆に頭が痛くなりますが、
完全5度と言うのが全音のみで構成されないことや、3度の音のポジションで長調になったり短調になったりすることを知っていると役に立つと思います。
また、短調(ナチュラルマイナー)の場合は、この五度サークルの音を全体に短3度下げるとマイナーになります。ド(C)はラ(a)となり、そこを起点に時計回りにラ・ド・ミのミ(e)、ミ・ソ・シのシ(b)と言う具合です。
音楽の試験する訳ではないのでこんなことはどうでもいいように思いますが、♯や♭記号を見れば音階の調がわかりますのでどのコードで弾けばいいかわかります。と言うことは簡単な曲なら"なんちゃって伴奏"くらいはすぐ弾けると思います。
また、曲と言うのはその調で開始し、その調で終わるのが一般的なのですね。
ミ(E)の長調の曲(ホ長調)ならEのコードで始まり、Eのコードで終わるのですね。
実はそんなことは最近まで知りませんでした

コード進行がわからなくても、その調のスケールを繰り返し弾いていればそれなりに聞こえます(当然、転調しない場合です)
そういう事を中学でも教えて欲しかったなぁ~。
聞いてなかっただけかもわかりません・・・先生すみません・・・

西洋音楽において"12"と"5"と"3"と言ういう数字は重要だと思います。
12平均律。ギター(ガットギター)の指板もボディーの付け根がちょうど1オクターブ目の12フレット。
5度は上の5度サークルや3和音の構成音。
3度(短3度と長3度の中間)は完全5度の丁度真中の音ですね。どちらに傾くかで長調か短調かが決まる大切な音ですね。
数学的なことはよく分かりませんが、勉強するとおもしいですね。
でもギターが上手くなる訳ではありません