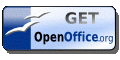2010年12月3日
このブログサイトは「昭和のすたる」に統合します。
「昭和のすたる」の音楽ネタ、英語ネタ、書籍ネタなどをここで紹介してましたが、「昭和のすたる」に統合します。昭和のすたるのブログサイトへ行くにはここをクリックしてください。
2010年9月24日
Take me to a Faraway field!
2010年9月8日
ESTAサーバーダウン中?
ESTAの申請が今日から有料。
昨日まで無料だったのが$14ですから大きいですね。
なんとか昨日駆け込めた方はよかったですね。
昨日はサーバーアクセスが集中していたようでレスポンスはあまりよくなかったですね。
で、本日は?
現時点ではどうやらダウンしている模様です。
申請の結果を確認したくても出来ない状況ですね。
昨日申請して今日渡航するような人はどうするのでしょうか?
2010年9月7日
ESTAの申請が有料に
この円高は海外旅行者にはありがたいのですが、企業は大変ですね。
さて、USへのビザ無し渡航(90日以内の短期旅行)はESTAの申請だけでよかったのですが、その申請に$14かかるようになります。
明日からです。
たぶんUS時間なので、まだ間に合いますね。急げ!
ESTA申請のサイトhttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html
2010年8月24日
2010年7月25日
ビウエラ・デ・マーノ
この前、ミランのパバーナⅡが難しくて・・・
ギターではなくリュートの曲なのでしょう。
と書きましたが、リュートではなくビウエラ・デ・マーノと言う楽器だそうです。

【El maestro(1536) より、ビウエラを弾くオルフェウス】
ミラン(Luis Milan)のことが気になって、パバーナⅡの曲も探していたのですが見つからず。
諦めかけていたらAmazonのマイページに
-「ルイス・デ・ミラン(1500-61);ファンタジア、パヴァーヌ、ガリアード集」
がお勧めとして出てました。
このCDの中の演奏者の一人であるJordi Savallをググってみると、なんとYouTubeで動画投稿されています。曲はパバーナⅡではないのですがビウエラ・デ・マーノを弾いている人がいます。この人はJordi Savallではありません。彼はヴィオラ・ダ・ガンバ(ビウエラ・デ・アルコが先祖)を弾いているひげの人です。
中世ルネサンスの頃の曲は独特の雰囲気がありますね。
ちなみに上述のCDに入っているパバーナⅡは、私の持っている楽譜の曲とは違いますね? YouTubeで探してもCDのものと同じ曲のものしか見つかりません。
と言うことで楽譜(正しく学べるたのしいギターレッスン=2 日本教育ギター振興会編)の曲の音源は謎のままです・・・
ちなみにパバーナ(パバーヌ)と言えばラベルの亡き王女のためのパバーヌが有名ですね。この曲もいつか弾いてみたいです。
2010年7月21日
猫ふんじゃった
鉄道員はなんとか弾けるようになりましたので、ミランのパバーナⅡ(6つのパバーナのうち2番目)を弾いていたのですが・・・
これが難しい
ルネサンス(1500年頃)の曲と言うことですから日本で言えば室町時代。
バッハの時代より100年以上も昔ですね。
ギターではなくリュートの曲なのでしょう。
私が、チンタラとぎこちなく弾いたのでは曲にならず・・・
ちっとも面白くなかったのですが、先生が弾くとリュートの響きがします。流石です。
いい曲だったのですね。
かなり速め(♩=160位)に弾かないとその感じが出ないので目下挫折中。
レッスンではこの曲は飛ばしているそうなので、私もお言葉に甘え飛ばします。
でも、いずれ弾きたい。
そのような訳で、目下、「猫ふんじゃった」を弾いてます
コード的にはD、A7、Gだけなので簡単。
D=トニック(Ⅰ)
A7=ドミナント(Ⅴ)
G=サブドミナント(Ⅳ)
です。でも今回はスラーの練習。
クラシックギターを始め1年4ヵ月、やっと特殊技法のレッスンです。
スラー、グリッサンド(アラストレとポルタメント)、トレモロ、トリル、ピチカート、ビブラートなど大変ですね。
また悪いクセが出てきているので注意しないといけません。
2010年6月28日
ラリーカールトンとB'zの松本孝弘
がコラボ。
このブログではギターについてウダウダと書いていますが、そもそも私がギターに熱中するきっかけになったのがB'zの松本孝弘さんです。
当然私もエレキギターからスタート。
なんとフェルナンデスのZO-3(ぞうさん)と言うアンプ内臓ギターからスタートし、ストラト、レスポール、PEAVEYのEVH(アンバーサンバースト・メイプルネック)と変遷。その間ギターの腕は上がらず・・・基礎力強化を目的にアコギを開始。これもおもちゃみたいなPEAVEYのアコギからスタートし、OVATIONのアダマスCharモデル(安かったので)、Parker初のアコギ(P8E)。
これでいくぶん基礎力は付きましたが悪いクセもつきました。
そして今ではすっかり落ち着いて、雑な造りのガットギター一本でクラシックギターの練習に励んでいます。悪いクセは一年経ちますがまだまだ直ってないようで・・・
こうなるとクセと言うよりもそもそも正しく出来ないだけかもわかりません・・・
2010年6月10日
ボケ味が美しい
SONY α(アルファ)NEX-3&5.
TV CMを見ているとその"美しいボケ味"がよくわかります。
一眼レフなみの描写力。
しかし一眼レフだからボケ味が美しい訳ではなく「被写界深度が浅いからボケ味の効果が出る」と考えた方が正しいですね。
一眼レフに広角レンズをつけて絞りを最大値(f値が大きい値)まで絞って写真を撮ってもボケ効果は出ません。
αはミノルタカメラのブランド名ですね。
ミノルタのレンズ"ロッコール"はその描写力がポートレートに向いていたようです。
TV CMを見ているとその"美しいボケ味"がよくわかります。
一眼レフなみの描写力。
しかし一眼レフだからボケ味が美しい訳ではなく「被写界深度が浅いからボケ味の効果が出る」と考えた方が正しいですね。
一眼レフに広角レンズをつけて絞りを最大値(f値が大きい値)まで絞って写真を撮ってもボケ効果は出ません。
被写界深度は焦点距離の長いレンズ(望遠)が浅く、また絞りが大きい(f値が小さい)ほど浅いです。
浅い=ピントが合う範囲が狭い=ボケ効果が強い
また、一般に一眼レフはコンデジよりCCD(銀塩カメラのフィルムに相当)が大きく、描画性能もいい(許容錯乱円が大きい)ので"美しいボケ味"が期待できるのですね。
また、一般に一眼レフはコンデジよりCCD(銀塩カメラのフィルムに相当)が大きく、描画性能もいい(許容錯乱円が大きい)ので"美しいボケ味"が期待できるのですね。
で、理屈は兎に角、"一眼レフ=美しいボケ味"となる訳です。
SONY α(アルファ)は、一眼レフなみのCCDとE18-55mmF3.5-F5.6(35mmフィルム換算で27mm-82mm)のレンズを絞り開放で使って一眼レフと同じような美しいボケを実現するのですね。
コンパクトデジカメでも被写界深度を理解していればボケ効果の高い写真を撮影することも可能ですが、条件がいくぶん厳しいと言うことですね。
ズームレンズを55mm側にシフトし、絞りをF5.6にし、さらに被写体に近づいて撮影した時にもっともボケ効果は高くなります。それが下のCMで北川景子さんが、タンポポをバックにオルガンの鍵盤を撮影しているシーンですね。
SONY α(アルファ)は、一眼レフなみのCCDとE18-55mmF3.5-F5.6(35mmフィルム換算で27mm-82mm)のレンズを絞り開放で使って一眼レフと同じような美しいボケを実現するのですね。
コンパクトデジカメでも被写界深度を理解していればボケ効果の高い写真を撮影することも可能ですが、条件がいくぶん厳しいと言うことですね。
ズームレンズを55mm側にシフトし、絞りをF5.6にし、さらに被写体に近づいて撮影した時にもっともボケ効果は高くなります。それが下のCMで北川景子さんが、タンポポをバックにオルガンの鍵盤を撮影しているシーンですね。
【ライバル機OLYMPUS。宮崎あおいさんのCMがいい!】
αはミノルタカメラのブランド名ですね。
ミノルタのレンズ"ロッコール"はその描写力がポートレートに向いていたようです。
ボケ味がよかったのでしょうね。
関西の企業なので六甲からとってロッコールなのですね。
ところで、青山霊園でヌード写真を撮り罰金30万円の判決が昨日言い渡された篠山紀信さんがミノルタXEのCMに出てました。
それと雑学王の名がすっかり定着した宮崎美子さんもミノルタのCMがデビュー作ですね。
ところで、青山霊園でヌード写真を撮り罰金30万円の判決が昨日言い渡された篠山紀信さんがミノルタXEのCMに出てました。
それと雑学王の名がすっかり定着した宮崎美子さんもミノルタのCMがデビュー作ですね。
さらに海外ではハリウッドスターのキャンディス・バーゲンがXDのCMに出てました。
ミノルタブランドとロッコールブランドはなくなったのですがαブランドは生き続けて欲しいですね。
2010年6月6日
It's Cool ~ It's a SONY
と言う響きが懐かしい。


子供の頃はSONY製品にあこがれたものです。
その先進性とデザイン。
特にデザインはシンプルでかつメカニック(電子製品なのに)
それがいつしかSONYブランドは神話の世界に・・・
が・・・
久々にSONYらしいデジタルカメラが。

ミノルタを買収しα(アルファ)ブランドと高い技術力をSONYのクールなデザイン力で形づくったNEX。
名前がPEPSIみたいでイケてませんが、そのデザインとコンセプトはGood!
OLYMPUS Pen E-P1の対抗機種として十二分の十力を持っていそうです。

と言うことで今回は、ギターにも英語にも読書にも関係ない話しでした。
【NEX-5で撮影したサンプルMovie】
2010年6月4日
電子書籍にシフト
最近、ギターネタばかりなのですが・・・
今年の目標はTOEICで600点超えと、読書だったハズ。
TOEICの方は来月でチャレンジして丁度1年目。
年始に受けたTOEICの試験で辛うじて500点超えたばかりですが、その後は学習が滞っていて来月の受験は断念ですね。
あと半年間しっかり勉強して来年初の試験で600点超えを目指します。
さて、読書の方ですが、こちらの方はぼちぼち。
iPhoneのSkybookで夏目漱石を読破する予定です。
こころ、明暗、三四郎、それから、門、虞美人草、草枕、彼岸過迄、坊ちゃん、道草・・・
ビジネス書もぼちぼち。
"ロングテール"の言葉で有名なクリス・アンダーセンの「フリー」目下読書中。これはおもしろいです。
今年のベストセラー1Q84BOOK3についで第2位の「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」は、iPhone版を購入。(本当はiPad版がよかったのですがiPadを持っていない・・・)
単行本だと¥1680でiPhone版だと半額以下の¥800とお買い得です。
と言うことで、どんどん読書が電子書籍版の方にシフトしている状況です。
iPad買えば、その傾向はますます加速し、読書量も加速するような気がします。
そういえば佐々木俊尚さんの「電子書籍の衝撃」をAmazonで購入したので、今日あたり届きそうです。これも電子書籍が出ています。Amazonのロープライス版のが安かったのでそちらにしましたが、嵩張るので電子版にした方がよかったかな?と思っています。
もし私がiPadを持っていて、電子書籍が紙の書籍の半額程度で出ていれば、躊躇なく電子書籍を買うと思います。
と言うことで読書量は少ないのですが、ぼちぼち読書にも時間を割くように心がけています。
2010年6月1日
5度サークルは指板の上に

5度サークルは調の基本になるので憶えておきたいところですが暗記するのも・・・
5度サークルなので順番に数えれば分かるのですがそれも・・・
と言うギター弾きには便利な道具が!
そう。ギターそのものです。
ギターの調弦は通常各弦間が4度(転回形で5度)のインターバルです。(2弦-3弦間は長3度)
高音弦に向かっては4度、低音弦に向かっては5度のインターバルです。
例えば5弦3フレットはCで同様フレットの6弦はG(これが5度の音)同様フレットの4弦はF(これが4度の音)となります。
5度サークルは時計回りに5度進行で反時計回りに4度進行なのでギターの指板とほぼ同じ。
問題は2弦-3弦間は長3度なので、この部分はつかえません。
しかし、なぜ2弦-3弦間だけが長3度なのでしょうか?
確かに2弦-3弦間を長3度にすることにより1弦と6弦は同じ音になりますし、2弦も6弦をルート音にした場合は5度、5弦をルートとした場合は短3度、3弦をルートとした場合は長3度となりコードを作りやすですね。
本当の理由は何か?
ご存知の方がいらしたらお教えください。
【閑話休題】
iPadの評判がすごいですね。
朝日新聞には2日にひとつくらいはiPad関連記事が出ています。
電子書籍や新聞、雑誌などへのコンテンツ閲覧デバイスとしての期待感が高くなっているようです。
そう言えば、ソフトバンクの孫正義社長が教育現場にiPadなどのデジタルデバイスを配布し電子教科書化する構想を熱く語っていました。小学生から大学生までの全学生にiPadのようなデバイスを配布するそうです。
音楽の教科書が電子化すればいいですね。
5度サークルや和音などの勉強も効果的ですよね。
キーボードやギターやパーカションなどのアプリも使えば高い楽器を購入する必要もありませんよね。

2010年5月23日
エレキギター
「大人の科学」です。
4本弦です。
なんかビギンの"一五一会(いちごいちえ)"みたいです。
アンプとスピーカーは内臓しているのでフェルナンデスの"ZO-3(ぞうさん)"みたいでもあります。
調弦はどうするのでしょう?
太い方の弦からE・A・D・Gなのでしょうか?
ベースと同じですね。
ちなみに"一五一会"はG・D・G・Dなので指一本でパワーコード完成です。
Gを1度とするとDは5度なので1五1会なのですね!?
E・A・D・Gなら4弦ルートでコードを弾けば、majorとminorも使い分けれるし、7thなども使えるので問題なく演奏できそうですね。
でも、弾いてみたいと言うよりは、作ってみたくなりますね。
2010年5月20日
2010年5月14日
速弾き
は苦手です。
ピックを使っての速弾きも苦手でした。
昨年の今頃は、トレモロが全然できなくて・・・
様々なエクササイズを試しました。
一番効果があったのはデスクトップエクササイズ。
机の上に指を置いてタカタカとやる練習ですね。
これで速度は120位まではできるようになります。
でも、音の粒が揃わなかったり、安定してなかったりするので、pmaiの繰り返しをpiamaiでやってみるのも練習に混ぜてみる。
これも有る程度効果がありそうです。
と言うものの、相変わらずトレモロはまだまだ不十分な状態です。
そんな状況なのですが、スケールの速弾きに挑戦してます。
こちらはimの二本指で挑戦。
やってみて気づいたのですが、左手よりも右手の動作(imの繰り返し)が遅い。
右手と左手を別々に練習し、右手の動きを左手の速度までアップさせる訓練をし、両手を同期させる訓練を始めました。
トレモロと同じように来年の今頃は、いくぶんましになっていることを期待して頑張ります。
これも目標は120です。
2010年4月28日
鉄道員 ~ 懐かしい映画
フランス映画やイタリア映画が全盛だった1950年代のイタリア映画。
鉄道員。
今、この曲を練習しています。
色々なアレンジがあると思いますが、私が練習しているのは比較的簡単に弾けるアレンジのものだと思います。
簡単なようで案外難しいです。
これもメロディの部分はアポヤンドで弾きます。
伴奏部があまり大きい音だと美しくないそうですが、どうしてもても大きく弾きがちです・・・
ところで、1950年代のイタリア映画には名作が多いですね。
「禁じられた遊び」「道」などもは有名です。
「道」は巨匠フェデリコ・フェリーニの作品です。
大道芸人に買われて、一緒に旅する白痴の女性ジェルソミーナをジュリエッタ・マシーナが好演しています。
私は、ウッディ・アレンの「ギター弾きの恋」のハッティ(サマンサ・モートン)を見た時、ジェルソミーナと重なりました。何か仕草とか表情がとても似ていた。
「ギター弾きの恋」は、ジプシーギター(スイングギター)なのでなかなか弾くのが大変ですが、「鉄道員」「禁じられた遊び(愛のロマンス)」「道(ジェルソミーナのテーマ)」はクラシックギター用にアレンジしたものが初中級のレベルで弾けそうですので練習したいと思います。
2010年4月21日
アポヤンド嫌い派
だったのですが、そんな私も、クラシックギター2年目に突入。
アコギを少しかじってついた悪いクセはまだ取りきれていないのですが・・・
一番最初につまづいたのは爪で弾くこと。
そしてアポヤンド奏法。
簡単な単音のメロディーはなんとかアポヤンドで弾けますが、親指と同時に高音弦をアポヤンドで弾くのは苦手。
しかし、トレモロの練習をしていて気づいたのですが、正しくアポヤンドできないとトレモロは難しいのではないか?
指を鷲づかみのようにしてアルアイレでアルペジオをかき鳴らすことはできても、鷲づかみの手でトレモロは無理のような気がします。
第一・二関節を柔軟にして撫でるような指使いがトレモロには望まれますし、アポヤンド奏法も同様。アルアイレ奏法も基本的にはその延長線上で、第一関節を曲げるか伸ばすかの違いではないかと思います。
私はアコギではほとんどピック弾きだったので指でかき鳴らすような奏法には馴染みがなかったのですが、それでもアポヤンドは苦手でした。
アコギでアルペジオの指弾きに慣れた方などは、かきむしり派の方も多いのでは?
そのような方はアポヤンドは苦手ではないかと思います。
その時は、アポヤンドでトレモロの練習をしてみてはどうでしょうか?
ちなみのアコギの指弾きがなぜかきむしり派になるか?
それは爪で弾かないからだと思います。
そうなるとやはりクラシックギターの命は爪と言うことになるのでしょうか?
2010年4月18日
ポジションマーク
2010年4月4日
ライオンとウルフのBlueNote
ブルーノートは1939年にアルフレッド・ライオンにより創設されたジャズレコードレーベルですが、1939年に録音されたアルバート・アモンズの「ヴギ・ウギ・ストンプ」から始まり2002年のダイアン・リーブスの「リフレクション」までのブルーノートのオムニバスCD二枚組み(全24曲)もついています。
ちなみに、写真家フランシス・ウルフはアルフレッド・ライオンの幼馴染みてあり二人ともにベルリン生まれです。なんと名前を見るとライオンとウルフ?強そうですね。
1939年と言えば第二次世界大戦勃発の年、ユダヤ系ドイツ人のアルフレッド・ライオンはその前にアメリカに移って来ていたのですね。
これからジャズを聴きたい人。
今まで耳にはしていたけど誰の何と言う曲か分からなかった人。
古きよき写真の頁をめくりながらゆったりとジャズを楽しみたい人。
いろいろな人が楽しめる写真集&CDだと思います。
【CDに含まれている曲】
CD1
1.Albert Ammons - Boogie Woogie Stomp 1939年録音
2.Sidney Becht - Summertime 1939年録音
3.Thelonious Monk - Criss Cross 1951年録音
4.Bud Powell - Bouncin' With Bud 1949年録音
5.Clifford Brown - Easy Living 1953年録音
6.Horace Silver - Senior Blues 1956年録音
7.Hank Mobley - Frank in Deep Freeze 1957年録音
8.Jhon Coltrane - Lazy Bird 1957年録音
9.Art Blakey And The Jazz Messengers - Mornin' 1958年録音
10.Dexter Gordon - Cheese Cake 1962年録音
11.Herbie Hancock - Maiden Voyage 1965年録音
12.Bobby Hutcherson - 'Til Then 1967年録音
13.Andrew Hill - Block Fire 1963年録音
CD2
1.Jimmy Smith - The Jumpin 'Blues 1960年録音
2.Ike Quebec - Easy-Don't Hurt 1961年録音
3.Wayne Shorter - Adam's Apple 1966年録音
4.Kenny Burrell - Chrislins Con Carne 1963年録音
5.Jhon Scofield - I'll Take Les 1993年録音
6.Jacky Terrasson - I Love Paris 1994年録音
7.Cassandra Wilson - I Can't Stand The Rain 1993年録音
8.Greg Osby - Miss D'Meena 1996年録音
9.Joe Lovano - Duke Ellington Sound Of Love 1995年録音
10.Tim Hagas - Housewife From New Jersey 1993年録音
11.Dianne Reeves - Reflections 2002年録音
これからジャズを聴きたい人。
今まで耳にはしていたけど誰の何と言う曲か分からなかった人。
古きよき写真の頁をめくりながらゆったりとジャズを楽しみたい人。
いろいろな人が楽しめる写真集&CDだと思います。
【CDに含まれている曲】
CD1
1.Albert Ammons - Boogie Woogie Stomp 1939年録音
2.Sidney Becht - Summertime 1939年録音
3.Thelonious Monk - Criss Cross 1951年録音
4.Bud Powell - Bouncin' With Bud 1949年録音
5.Clifford Brown - Easy Living 1953年録音
6.Horace Silver - Senior Blues 1956年録音
7.Hank Mobley - Frank in Deep Freeze 1957年録音
8.Jhon Coltrane - Lazy Bird 1957年録音
9.Art Blakey And The Jazz Messengers - Mornin' 1958年録音
10.Dexter Gordon - Cheese Cake 1962年録音
11.Herbie Hancock - Maiden Voyage 1965年録音
12.Bobby Hutcherson - 'Til Then 1967年録音
13.Andrew Hill - Block Fire 1963年録音
CD2
1.Jimmy Smith - The Jumpin 'Blues 1960年録音
2.Ike Quebec - Easy-Don't Hurt 1961年録音
3.Wayne Shorter - Adam's Apple 1966年録音
4.Kenny Burrell - Chrislins Con Carne 1963年録音
5.Jhon Scofield - I'll Take Les 1993年録音
6.Jacky Terrasson - I Love Paris 1994年録音
7.Cassandra Wilson - I Can't Stand The Rain 1993年録音
8.Greg Osby - Miss D'Meena 1996年録音
9.Joe Lovano - Duke Ellington Sound Of Love 1995年録音
10.Tim Hagas - Housewife From New Jersey 1993年録音
11.Dianne Reeves - Reflections 2002年録音
2010年3月29日
2010年3月27日
2010年3月24日
2010年3月22日
木村カエラの後は発表会
昨日は、1年間続けたクラシックギターの合奏発表会でした。
WOWOWで木村カエラの横浜の赤レンガパークライブを放送してたのでそれを見てからの発表会。
カエラでも見て、いくぶんテンションをあげようと思ったのですが、どうも緊張感のないままにステージへ・・・
「アルハンブラの思い出」と「Ob-La-Di,Ob-La-Da」の2曲は10分足らずで終わってしまいました。
ステージはどうも音のバランスが悪かったようですが、隣の方の音と自分の音はよく聞こえました。客席へは?
途中2小節ほどパスしたりもしましたが、そこは合奏の強み。
片肺飛行も可能な双発機ですので私よりはるかに上手な方がしっかり弾いていてくれました。
と、言うことで緊張感のないまま不完全燃焼に終わってしまいました。
今週末も同じ曲で小さな舞台に立ちますが・・・
いい意味でもう少し緊張感を持って望みたいと思います。
2010年3月10日
かんたん楽譜の読み方~楽譜読めない派の方に
楽譜を読めなくて楽器の演奏を断念している方は多いと思います。
ギターはコードを憶えてしまえば有る程度は楽しめるポピュラーな楽器なのですが、それだけだと物足りなくなりますね。
クラシックギターの場合ですと楽譜が読めないと厳しいです。
私は絶対音感がないので楽譜を見ても歌えません。
また、初見でサクっと弾くこともできないですし、裏拍の取りかたも下手。#や♭がいっぱい出てくると混乱するし・・・
でも私と同じような人は多いと思います。
このサイトでは、「5度サークルがどうだ」とか「メロディックマイナーはメジャースケールの3度が短3度になっただけ」とか、ウザウザ書いていますが、実は私は"楽譜読めない派"なのです。
そんな私が最近出あった本。"かんたん楽譜の読み方"
"楽譜読めない派"の私でもギター暦はぼちぼち10年になろうかとしてます。
いまさら手にするのが恥ずかしいようなタイトルの本なのですが・・・
最初の方のページは本当に楽譜が苦手な人には分かりやすくお勧めです。
また、テストのページなどもあり、いくぶん楽譜を読める人でも復習を兼ねて読めば楽しめます。
文章は短いのですが、とても丁寧に書かれているので理解しやすいです。
最後は簡単な音楽理論について書かれています。頁数は少ないのですが、この部分が優れものです。必要最小限の事が丁寧に記述されています。
完全4度や5度、テトラコード、主音や下属音や導音の関係から始まり、5度サークルや調の早分かり方法など。
本質的で実践的なことがとても簡潔にまとめられているように思います。
音楽理論本をいきなり手にするよりも、この本でまず勉強すればいいのではないかと思います。少なくとも私のような"楽譜読めない派"の人にはお勧めの本です。
この本を著された幡野 友香には、ぜひ「かんたん音楽のしくみ」などと言う本を書いて欲しいくらいです。
2010年3月6日
気合を入れて合奏の練習
合奏発表会が2週間後に迫りました。

私のクラシックギター教室でのGOALは「アルハンブラの思い出」のソロなのですが、今回は合奏で伴奏パートを担当。来年の今頃はソロの練習をしているハズ。
と言う具合に気持ちばかりが先行。
TOEICの600点超もまだまだ遠いですしね・・・
とりあえず2カ年計画の中間点通過と言うことでがんばります。
iPhoneアプリについては有料バージョン出しましたね。
TOEIC 650点を目指せ!
¥1300です。iPhoneアプリとしては高い気もする。
無料版のiPhoneアプリは品質が悪く使い物にならなかったですが、有料版はきっと使えるのだと思います。
まずはWebサイトのsmart.fmに復帰し、ちゃんとこなしてから購入を検討します。

2010年2月23日
あぁ~遠い600点
2010年2月15日
楽譜を見て最初にやること
クラシックギターを始めて10カ月が経過。
楽譜を見て最初にやる事は

楽譜を見て最初にやる事は
"調"が分かれば後は"コード(和音)"を導き出します。
これも難しく考える必要はなく、その"調のスケール"上に登場する音から3度、5度、7度を積み上げれば自ずとコードが決まります。
※テンションノートなどと言う9度,11度,13度などもありますがここでは省略
たとえばおなじみのハ長調(C Major)
たとえばおなじみのハ長調(C Major)

これが演奏力にどうかかわるかはさておき、私が楽譜を見た時に一番最初にやることで、結構楽しい作業です。
またコードの押弦フォーム(ポジション毎に何パターンもあります)は、クラシックギターでも少しは役に立つと思っています。
でも、私のギターの先生は「百害あって一利なし」みたいに仰います。
押弦が必要のない弦まで押さえたりしてしまい注意される事もあります。
それでも私が楽譜を見て最初にやることは"調の確認"と"コード(和音)の整理"です。
2010年2月11日
マイナースケール~指板ポジション
 Aマイナースケールの指板ポジションを掲載します。
Aマイナースケールの指板ポジションを掲載します。毎日の練習はこの指板ポジションでエクササイズ。
"メロディックマイナー"で上昇し、"ナチュラルマイナー"で下降します。
マイナースケールはこれ以外に"ハーモニックマイナー"と言うのがあることは以前にも書きましたが、"ナチュラルマイナー"は"メジャースケール"の3度下から開始(Cmajor=Aminor)したスケールで"ハーモニックマイナー"は"ナチュラルマイナー"の7度が半音上がったものです。
スケールの練習は指板ポジションを憶えるだけでなく、指の開きとか、形、移動の仕方などに注意し、スムースに弾けるようにすることが大切のようです。
地味なエクササイズですが、拍子に変化を加えるなどの工夫をして楽しく続けたいと思います。
効率よく憶えるためには、同一フレット上の上下弦の音も一緒に憶えればいいですね。。
上弦には5度の差があり下弦については4度の差があります。(2-3弦以外)
たとえば3弦のEと同一フレット上の4弦はB(Eをルートとすると5度の音)、3弦はA(Eをルートとすると4度の音)です。
和音を思い浮かべ(EならE-G#-B)れば5度の音はすぐ出てきますね。
5度はBなら4度はAと言う具合なので簡単ですね。
でも、相対的にポジションを憶えるのは最初の段階だけ。
最終的には絶対的なポジションを憶えてしまわないと演奏には間に合いません・・・
それでも相対的にポジションを理解することは、コード押弦には役に立ちます。
2010年2月8日
あっ忘れてた・・・
先週の土曜日はギタースクールでした。
が、すっかり忘れていました。
月に2回のレッスンなのですが・・・
次は2月20日です。
3月にある合奏の練習をしなければいけないのですが練習に身が入らず怠けがち。
ついでにレッスンまで忘れてしまう始末。
ぼちぼちハイポジションの曲も練習しなければいけないのですが、まだ指板のポジションが充分に覚えられていません。
毎日、スケールの練習が必要ですね。
Aメロディックマイナーを5弦開放から開始し、3オークターブ上のAまで上昇し、ナチュラルマイナーで下降する練習をすることにしました。
上昇時がメロディックマイナー(6度と7度が#)で下降がナチュラルマイナー(Cメジャーと同じポジショニング)なので、少し集中力が必要です。
また、上昇時と下降時はいくぶん運指にも変化がある。
上昇時は
5弦:A-F#
4弦:G#-D
3弦:E-G#
2弦:A-C
1弦:D-A
下降時
1弦:A-D
2弦:C-A
3弦:G-D
4弦:C-E
5弦:D-A
となります。
これを毎日の練習に取り入れていけばハイポジシションも怖くない!?
ところでトレモロの方は?と言うと・・・
粒がそろわないですね。
これは慣れ(手グセ)で弾く前に、しっかり指の動きを見ながら練習する必要がありますね。
視覚を駆使しての訓練をしたいと思います。
2010年1月31日
2010年1月18日
めっちゃ下手(2)~虚脱の進め
本年度最初のギター教室で、拙い演奏もなんとか披露。
55秒のショートショート演奏(エスパニョレッタ/サンス)でしたが、大きなミスもなく無事演奏。
教室は普通の部屋なのですが、ギターの音がとてもよく響く。
前にいらっしゃる生徒さんのギターが、丁度いい音響効果になっているのですね。
おかげで下手な演奏もなんとか上手に聴こえたような気がします。
演奏を披露する直前に合奏の音合わせ。
オブラディオブラダとアルハンブラ宮殿の思い出のベースパートなのですが、ほとんど練習してないままでの音合わせ。
合うハズもなく(そもそも弾けません)、どっと疲れた状態で演奏披露。
前に出た時は、緊張することもなく演奏できました。
いい感じで肩の力が抜けたこの状態が、大切なのですね。
でも、意識してもなかなかこの状態は作れません。
丁度、センター試験日でしたが、受験生が緊張を緩める方法として「首の後ろで手を組む。」と、言うのがありますが、これは緊張して冷えた指先を温める効果があります。また、頭(顔)の近くを手で触れることで、精神的に安心する効果があるのかもわかりません。
これが本当に効果があるかどうか?時々試してみたいと思います。
ただし、最初から虚脱状態では効果が無いように思います。
一度緊張(集中)状態を作った後に、脱力状態を作れば丁度いい状態になるのでしょうか?
虚脱と言うのは大げさで脱力と言った方がいいですね。
今回は、自然にそのような状況が出来ていたのでしょうね。
今度は、意識的にそのような状況を作って、その効果を試してみます。
2010年1月15日
めちゃ下手・・・
明日は今年最初のギター教室日。
もう寒すぎで練習もサボリがちなのですが明日はみんなの前で演奏しなければいけません。
このギター教室は、毎回練習の最後に誰かひとり前に出て演奏します。
場馴れにはいい訓練かもわかりませんが・・・
で、できるだけ短めのを選んで練習しました。
そしてiPhoneで録音。
うぅぅ・・・下手。聴くに堪えない・・・
間違うのはまだいいとして音楽として聴くに堪えませんね。
あ~ぁ。明日はこんなんで披露しなければいけないなんて。
自分の演奏を録音して聴くのは勇気いりますね。
でもこれが大切なんですね。
そんなこんなで3月にやる合奏の譜面はいただいているのですが練習してません。
寒すぎでどうも気合いが入りません。
一月早々にこんなことで情けないですね・・・
そういえば先週TOEICの模試はしたのですが2時間で力尽き、答え合わせはまだです。
明日、ギター演奏披露で落ち込んだ気持ちで答え合わせをします。
これを乗り切れば明るい未来があるでしょう。
明日は受験生もセンター試験で頑張っているのですからね。
2010年1月11日
2010年1月4日
あけましておめでとうございます
今年は、クラシックギター教室卒業(できるか?)。
TOEIC600点オーバー(大丈夫か?)。
何かスポーツをやる(まだ決めてません・・・)。
本を読む(どんな本なの?)。
と言うことでゆるぅ~く過ごしたいと思います。
登録:
投稿 (Atom)